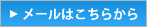先日参加した労働法に関する講演会での、ある弁護士の言葉が非常に印象に残りましたので、紹介したいと思います。
「労働法は難しい。そして、裁判結果は“水物”だ。」
まさに、私たち社労士や人事労務担当者が日々感じている現実ではないでしょうか。
労働法は、他の法律と比べても不確実性が高く、「こうすれば必ず正解」というルールが存在しない世界。
今回は、その“難しさ”の正体と、私たちがどう向き合うべきかを考えてみたいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 労働法が「難しい」と言われるワケ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
✓ 契約より“実態”が重視される
たとえ業務委託契約を結んでいても、実際の働き方や指揮命令の状況によっては「労働者」と判断されることも。
→ 書類の整備だけではリスクは回避できません。現場の実情こそが問われます。
✓ 条文より“判例”が命
抽象的な法律文言だけでは判断できず、実務上は過去の"判例"が重要な指針になります。
→ つまり、常に「今の流れ」にアンテナを張る必要があるのです。
✓ 「同じケース」は存在しない
似たような事案でも、社員の勤務状況や会社の対応などが違えば、判断も変わる。
→ 裁判結果が“水物”と言われる所以です。
✓ 契約自由の限界
一見フェアに見える契約も、労働者保護の観点から無効とされるケースも少なくありません。
→ 「会社の正しさ」だけでは通用しないのが、労働法のリアルです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 「グレー」に強くなる4つの視点
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こうした不確実性に対し、私たちができることは、「グレー」を恐れるのではなく、見極めて動くことです。
✓ 書面だけでなく、現場の実態を常に確認する
✓ 判例の変化をウォッチし続ける
✓ 類似事例の中にある“違い”に着目する
✓ 常に労働者保護の視点を持つ
「白黒はっきりしないことにどう対応するか」。
それが、私たち専門職の腕の見せ所でもあります。
だからこそ、学び続けること、情報をアップデートし続けることが、最も重要なのだと思います。